
「うちの子の発達障害は、私の育て方が悪いから?」
そう悩む親御さんは少なくありません。子どもの特性に戸惑い、自分を責めてしまうことがあるでしょう。
発達障害は、決して親のせいではありません。むしろ、子どもの独自の個性であり、適切な理解とサポートによって、その可能性を大きく伸ばすことができます。
この記事では、発達障害に関する正しい知識と、子どもと親への効果的なサポート方法について詳しく解説します。発達障害についての不安や疑問にお答えします。お子さんの特性を理解し、前向きに子育てを行うためのヒントとしてぜひ参考にしてください。
発達障害は親のせいではない

発達障害は生まれつきの脳機能の特性であり、親の育て方や愛情不足が原因ではないことが科学的研究により明らかになっています。かつては「冷蔵庫マザー理論」として、母親の愛情不足が自閉症の原因とされた時代もありましたが、この考えは1940〜50年代の古い理論であり、現在は完全に否定されています。
発達障害は、複数の遺伝要因と環境要因が複雑に絡み合って発症する「多因子遺伝疾患」(さまざまな要因が組み合わさって影響を与える状態)の一つとされています。一卵性双生児の研究では、片方が自閉症の場合、もう片方も50〜85%の確率で発症することが判明しており、遺伝的要因の強さが示されています。
発達障害に関連する遺伝子は多くの人が持っており、それが特徴の強弱として現れる可能性があります。そのため、親の育て方を責めるのではなく、子どもの個性として受け止め、適切なサポートを行うことが大切です。
発達障害のある子どもを持つ親の半数以上が子育ての方法に不安を感じているという調査結果もあります。しかし、これは発達障害の原因が育て方にあるということではなく、むしろ特性のある子どもの育て方に悩む親の姿を表しています。子育ての困難さを感じることは自然なことであり、親が自分を責める必要は全くありません。
発達障害の種類
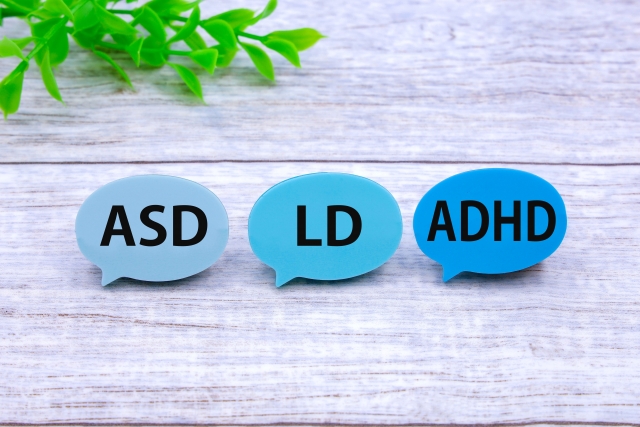
自閉症スぺクラム障害(ASD)の特徴
自閉症スペクトラム障害(ASD)は、対人関係やコミュニケーションの難しさ、特定のものへのこだわり、感覚の特異性などを特徴とする発達障害です。ASDの子どもは、他人との関わり方に独特のスタイルを持ち、社会的な状況の理解や適切な対応に課題を感じることが多くみられます。たとえば、相手の表情や言葉のニュアンスから気持ちを読み取ることや、場の空気を読むことに苦手意識を持つ傾向がみられます。
また、特定のものごとやルールに強いこだわりを示すところも特徴です。好きなことには熱中する一方で、興味のないことにはまったく関心を示さない場合も多くみられます。日常生活においては、同じ道順や手順へのこだわりが強く、予定の変更に対して強い不安を感じやすい傾向にあります。
さらに、特定の音や光、触感に敏感に反応する一方で、痛みに対してあまり反応を示さないことも特徴的です。こうした感覚の特性により、日常生活や学校での適応に様々な影響が生じることになります。
注意欠如多動性障害(ADHD)の特徴
ADHDは、不注意、多動性、衝動性という3つの主な特徴を持つ発達障害です。不注意の特徴として、物事に集中し続けることが難しく、忘れ物が多い、気が散りやすい、整理整頓が苦手といった様子を見せます。
多動性の特徴を持つ子どもは、じっとしていることが難しく、常に体を動かしている傾向にあります。たとえば、授業中に席を立ってしまったり、手足をそわそわと動かしたりする様子が見られます。衝動性については、考えずに行動に移してしまう、順番を待つことが苦手、会話の途中で突然話し始めてしまうといった特徴が現れます。
ADHDは子どもの約2%にみられ、男の子に多く見られる傾向にあります。ただし、全ての特徴が同じように現れるわけではなく、不注意が強く出るタイプ、多動・衝動性が強く出るタイプ、その両方が見られる混合タイプに分かれています。
一方で、ADHDのある子どもには様々な長所も見られます。好きなことには高い集中力を発揮でき、豊富なアイデアを生み出す創造性や、人とのコミュニケーション能力に優れた子どもも多くいます。これらの特性を活かすことで、子どもたちは様々な場面で活躍する可能性を秘めています。
学習障害(LD)の特徴
学習障害(LD)は、知的能力に問題がないにもかかわらず、特定の学習分野で著しい困難を示す発達障害です。主に読字障害(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカリキュリア)の3つのタイプがみられます。
読字障害のある子どもは、文章を読むのが極端に遅く、読み間違えが多くなります。一方で、同じ内容を耳で聞くと理解できることが特徴です。書字障害では、文字のバランスが取れず、マス目に収めることが難しかったり、「てにをは」の使い方を間違えたりする様子が見られます。算数障害の子どもは、数の概念を理解することが難しく、計算や推論に苦手さを感じています。
これらの特徴は小学校で本格的な学習が始まってから気づかれることが多く、学年相当より1〜2年程度の遅れとして現れます。周囲からは「努力不足」や「やる気がない」と誤解されやすいものの、これは子どもがなまけているのではなく、生まれつきの脳機能の特性によるものです。
また、学習面の困難さに加えて、聞く・話すなどのコミュニケーションにも影響が現れることがあります。たとえば、約束を聞き間違えたり、話の筋道を立てることが苦手だったりする子どもも多くいます。
発達障害の原因

遺伝の影響
発達障害は「多因子遺伝疾患」(複数の遺伝要因と環境要因が組み合わさって影響を与える状態)と呼ばれ、子どもの発達に様々な要因が関係しています。一つの遺伝子だけでなく、複数の遺伝子が環境との相互作用により影響を及ぼすことが分かっています。
遺伝の影響力を示す重要な研究として、一卵性双生児の調査があります。自閉スペクトラム症の場合、双子の一方の子どもが診断を受けると、もう一方の子どもも50〜85%の確率で同様の診断を受けることが明らかになっています。遺伝子が異なる二卵性双生児では、この確率が約20%まで下がることから、遺伝的要因の重要性が示されています。
発達障害に関連する遺伝子は、多くの子どもが持っているといわれています。これらの遺伝子は、その発現の強さによって特性として現れる可能性があり、必ずしも障害として表れるわけではありません。
また、発達障害の遺伝は単純な親子関係では説明できません。発達障害のある親から定型発達の子どもが生まれることもあれば、定型発達の親から発達障害のある子どもが生まれることもあります。このことからも、子どもの発達障害の発症には遺伝要因だけでなく、様々な環境要因が複雑に関係していることが分かります。
発達障害の原因は先天性
発達障害は生まれつきの脳機能の特性であり、通常のMRIやCT検査では発見できないほどの微細な脳の機能差によって生じています。これは病気というよりも、子どもの脳の発達過程で生じるアンバランスさによって特徴づけられる先天的な状態です。
発達障害に関連する遺伝子は多くの子どもが持っているという特徴があります。これらの遺伝子は、その発現の強さによって特性として現れる可能性があり、「あるかないか」ではなく「強いか弱いか」という個人差として捉えることが大切です。
さらに、胎児期の脳の発達過程における変化や、出生後の脳の発達に影響を与える要因も関係していると考えられています。このように、子どもの発達障害は単一の原因ではなく、様々な生物学的要因が組み合わさって生じる先天的な特性として理解することが重要です。
家庭環境は発達障害の直接的な原因ではない
「うちの子の発達障害は、私の育て方が悪かったから?」
そんな心配や自責の念を感じているお母さんは少なくありません。しかし、そのような心配は必要はしなくても大丈夫です。科学的な研究で、発達障害は生まれつきの特徴であり、親の育て方が原因ではないことが分かっています。
発達障害は、遺伝子や脳の発達など、様々な要素が関係して生まれる特徴です。そのため、家庭環境や親の育て方だけで発達障害になることはありません。
もちろん、子育ての環境は子どもの成長にとても大切です。発達障害のあるお子さんも、家族に理解され、適切なサポートを受けることで、より生き生きと過ごせるようになります。
心配なのは、虐待など極端に悪い環境で育った子どもの場合です。このような環境では、発達障害によく似た行動が見られることがあります。
発達障害の子どもと親のサポート方法

早期発見を心がける
発達障害の早期発見は、子どもの将来の自立した生活につながる重要な第一歩です。特に1歳6か月健診と3歳児健診は、発達障害の特徴に気づく重要な機会となります。これらの健診では、言葉の発達、対人関係、運動機能など、さまざまな側面から子どもの成長を確認します。
子どもの様子で気になることがあれば、健診を待たずに早めに相談することが大切です。「他の子どもと少し違う」「育てにくさを感じる」といった漠然とした不安でも、保健師や専門機関に相談することで適切な支援につながる可能性があります。
早期発見の目的は、単に「発見する」ことではなく、適切な支援につなげることです。発達障害は早期からの支援により、二次的な心理的・行動的問題を防ぐことができます。例えば、自尊心の低下やうつ症状、不登校といった二次障害を予防し、子どもが自分らしく成長できる環境を整えることが可能になります。
また、早期発見・早期支援は子どもだけでなく、保護者への支援も重要です。地域によっては、ペアレントメンターによる相談支援や、発達支援センターでの専門的なアドバイスなど、様々なサポート体制が整備されています。これらの支援を活用することで、親子ともに適切なサポートを受けることができます。
専門家に相談する
発達障害の相談窓口は複数あり、状況に応じて適切な専門家に相談できます。まず、各都道府県や指定都市に設置されている発達障害者支援センターでは、子どもから大人まで幅広い年齢層の相談に無料で対応しています。ここでは、日常生活での困りごとから就労に関する相談まで、総合的な支援を受けることが可能です。
医療機関では、精神科や心療内科で発達障害の検査や診断を受けられます。専門医による診察では、問診や心理検査を通じて、より詳しい状態の把握と適切な支援方針の検討が可能です。医療機関を選ぶ際は、発達障害の診療に対応しているか事前に確認することが重要です。
学校に通う子どもの場合、スクールカウンセラーに相談するのも有効な選択肢です。スクールカウンセラーは学校生活での困りごとに対して、子どもと保護者の両方をサポートできる身近な専門家です。また、必要に応じて外部の専門機関との連携も行います。
相談する際は、一つの機関に限らず、状況に応じて複数の専門家のサポートを組み合わせることで、より包括的な支援を受けることができます。早めに専門家に相談することで、子どもの特性に合った適切な支援を見つけやすくなるでしょう。
ペアレントトレーニングを利用する
発達障害の子育てに悩む親にとって、ペアレントトレーニング(ペアトレ)は非常に有効な支援プログラムです。このプログラムでは、子どもの行動を理解し、適切な対応方法を学ぶことで、より良い親子関係を築くことができます。
ペアトレは通常、1回90分程度、全6〜10回のセッションで構成されています。グループワークを通じて、同じような悩みを持つ保護者と一緒に学び合えるのが特徴です。講義とワークを組み合わせた実践的な内容で、学んだことを家庭で実践し、次回のセッションで振り返るというサイクルで進みます。
プログラムの核となる要素には、「子どものよいところを探し、ほめる」「子どもの行動を3つに分類する」「ABC分析による行動理解」などがあります。特に、子どもの好ましい行動に注目して具体的にほめることで、子育ての悪循環を好循環に変える方法を学べるのが大きな特徴です。
ペアトレは各都道府県の発達障害者支援センターや医療機関、保健センターなどで受講できます。費用は実施機関によって異なりますが、無料または数千円程度で利用可能なところが多いです。専門家のサポートを受けながら、子育てスキルを向上させ、自信を取り戻すチャンスとして、ぜひ活用を検討してみてください。
発達障害に対する正しい知識を持つ
発達障害の特徴は一人ひとり異なり、同じ診断名でも症状の現れ方には個人差があります。例えば、特定の分野で優れた能力を発揮する一方で、別の分野では極端に苦手といった特徴が見られます。この得意・不得意の差は誰にでもありますが、発達障害がある人はその差が非常に大きいのが特徴です。
発達障害の診断には、「先天性」「恒久性」「困り感」の3つの要素が重要とされています。先天性は生まれつきの要因があること、恒久性は特性が一貫して様々な場面で見られること、困り感は日常生活や社会生活に支障をきたしていることを指します。
大切なのは、発達障害を個性として捉え、その子どもの長所や得意分野を伸ばす視点を持つことです。早い段階で対応することで子どもの可能性を最大限に引き出し、自尊心を育むことができます。そのためには、家族や周囲の大人が正しい知識を持ち、適切なサポートを行うことが重要です。
発達障害に対する偏見を克服する
発達障害は「直さなければならない問題」ではなく、その子どもならではの「個性」の一つです。「普通の子と変わらないね」「頑張れば良くなるよ」という言葉は、励ましのつもりでも、発達障害への理解不足から生まれた偏見かもしれません。
最近では、障害のある子もそうではない子も一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」が広がっています。子どもたちが一緒に過ごすことで、お互いの違いを理解し、認め合う心が育ちます。これは将来の社会全体の偏見をなくすことにもつながります。
重要なのは、発達障害のある子どもに無理な努力を求めないことです。周りの人たちも発達障害について理解を深め、必要な手助けをする姿勢が大切です。一方的に子どもに頑張りを求めるのではなく、みんなで支え合う関係を作ることが必要です。
まとめ

発達障害は先天的な脳の働きの違いであり、環境や家族関係が直接の原因とはなりません。これは様々な遺伝的背景と成長過程での要因が組み合わさって生じる複合的な特性として研究で明らかになっています。
発達障害は、できるだけ早い時期からの気づきと適切なケアによって、子どもたちは持てる可能性を十分に発揮できるようになります。医療機関への受診やサポートプログラムへの参加など、多角的なアプローチを取り入れることで、より良いサポートが実現できるでしょう。
発達障害の子どもと生活する際に重要なのは、発達障害を個性として受け止め、その子どもの長所や得意分野を伸ばしていく視点を持つことです。周囲の理解と適切なサポートがあれば、どの子どもも自分らしく成長できます。ひとり一人の特徴に合わせたサポートを行いながら、共に成長していける社会を目指していきましょう。




