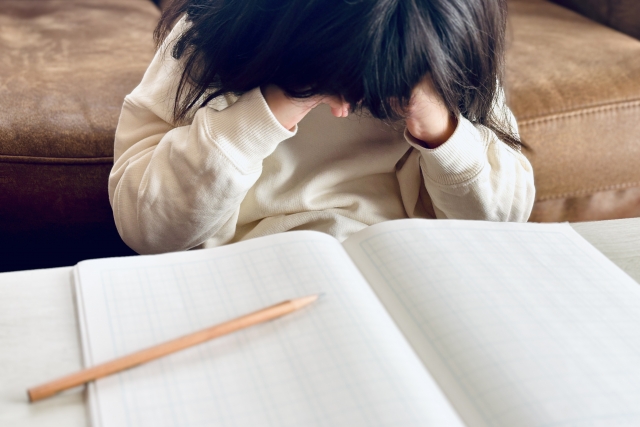
「何度教えても字を間違える」「本を読みたがらないのは、なまけているから?」
そんな風に子どものことで悩んでいませんか。
それは子どもの努力不足や、親であるあなたの教え方のせいではないかもしれません。
もしかすると、子どもには私たちとは全く違う世界が見えていて、文字を読むこと、書くことに困難を抱えている可能性があります。
この記事では、学習障害(LD)の子どもには文字がどのように見えるのか、そして家庭でできる具体的なサポート方法まで、わかりやすく丁寧にお伝えします。
子どもの「見えにくさ」を正しく理解し、前向きな一歩を踏み出すためのヒントがここにあります。
もしかして学習障害?文字の見え方が違う子どもたちの世界
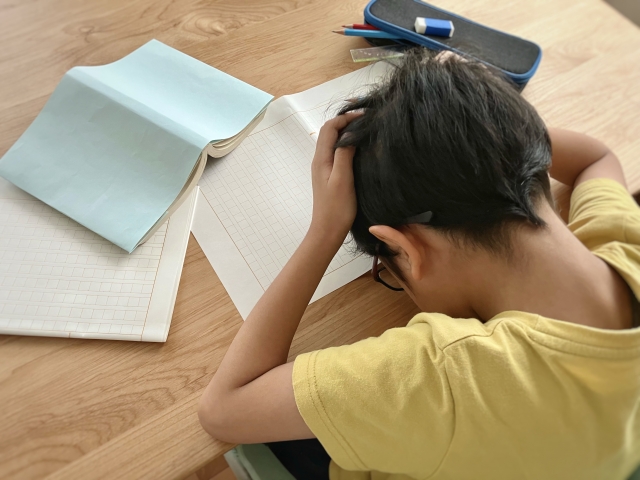
学習障害(LD)とは?努力不足ではない「脳の特性」
学習障害(LD)とは、知的な発達に遅れがないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力を学んだり使ったりすることに著しい困難を示す、脳の特性のことです。
決して本人の努力が足りないわけでも、なまけているわけでもありません。
情報の受け取り方や処理の仕方が、多数派の人たちと少し違うだけなのです。
特に文字の読み書きに関する学習障害は、「ディスレクシア(読字障害)」や「ディスグラフィア(書字障害)」と呼ばれています。
この特性は生まれつきのもので、周りからは気づかれにくいため、本人が「どうして自分だけできないんだろう」と一人で悩み、自信を失ってしまうことも少なくありません。
まず、子どもの困難さは「努力不足」ではないと理解することが、サポートの第一歩になります。
文字がゆがむ?にじむ?ディスレクシア(読字障害)の子どもの視点
ディスレクシア(読字障害)のある子どもには、文字が私たちと同じようには見えていません。
本人はそれが当たり前の世界なので、「見えにくい」と上手く伝えられないことも多いのです。
例えば、教科書の文字は以下のように見えているかもしれません。
- 文字がぼやけたり、二重になったりして見える
- 文字そのものがゆがんだり、動いたりしているように感じる
- 文字の黒い部分と白い背景がチカチカして、とても眩しく感じる
- 形が似た文字(「わ」と「ね」、「め」と「ぬ」など)が同じに見えてしまう
- 文章を読んでいると、どこを読んでいるのかわからなくなり、行を飛ばしてしまう
このような見え方では、文字を読むだけで非常に疲れてしまいます。
本を読みたがらない背景には、こうした切実な「読みにくさ」が隠れている可能性があるのです。
マスに収まらない?ディスグラフィア(書字障害)の子どもの視点
ディスグラフィア(書字障害)は、文字を読むことはできても、形を思い出したり、整えて書いたりすることに困難が生じる特性です。
頭の中では文字の形がわかっていても、いざ書こうとすると、手や指がイメージ通りに動かせないのです。
ディスグラフィアのある子どもには、このような困難さが見られます。
- マスや罫線の中に、文字をバランス良く収めるのがとても難しい
- 文字の大きさがバラバラになったり、傾いてしまったりする
- 鏡文字(左右反転した文字)を書いてしまうことがある
- 漢字のへんとつくりが逆になるなど、パーツの配置を間違えやすい
- 筆圧のコントロールがうまくできず、極端に濃い字や薄い字になる
何度練習しても字がきれいにならないのは、本人が不真面目だからではありません。
脳からの「こう書いて」という指令が、指先まで正確に伝わりにくい状態なのです。
子どもの「見えにくさ」をサポートする方法

UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)を使ってみる
子どもの「見えにくさ」や「書きにくさ」は、少しの工夫で大きく改善されることがあります。
特別なことではなく、毎日の学習環境を少し変えるだけで、子どもの「できた!」につながるかもしれません。
まず試してほしいのが、「UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)」の活用です。
UDフォントは、「ユニバーサルデザイン」の考え方に基づき、誰にとっても見やすく、読みやすいようにデザインされた特別な書体のことです。
文字の形がわかりやすく、濁点や半濁点も大きく表示されるなど、誤読しにくい工夫が凝らされています。
パソコンやタブレットに無料でインストールできるものも多く、宿題のプリントなどを作る際にフォントを変えるだけで、子どもが格段に読みやすくなる可能性があります。
まずは、Windowsに標準搭載されている「UDデジタル教科書体」や、無料で提供されている「BIZ UDフォント」などから試してみてはいかがでしょうか。
文字の大きさとスペースを調整する
文字が小さかったり、ぎゅうぎゅうに詰まっていたりすると、ディスレクシアの特性がある子にとっては非常に読みにくくなります。
そこで、文字の「大きさ」と「スペース」を調整するだけで、読みやすさが大きく改善されます。
家庭でプリントなどを作成する際は、教科書の文字よりもひと回りかふた回り大きいサイズに設定してみましょう。
さらに、文字と文字の間(字間)や、行と行の間(行間)を通常より広く取ることも効果的です。
スペースに余裕を持たせることで、一つひとつの文字が独立して認識しやすくなり、どこを読んでいるか見失いにくくなるというメリットがあります。
Wordなどのソフトでは簡単な設定で変更できるので、ぜひ試してみてください。
背景と文字の色を工夫する
真っ白な紙に黒い文字の組み合わせは、コントラストが強すぎて、かえって目がチカチカして読みにくいと感じる子どももいます。
これは「光の感受性が過敏」という特性が関係している場合があります。
もし子どもが白い紙を眩しそうにしていたら、背景の色を工夫してみましょう。
例えば、コピー用紙を真っ白なものではなく、淡いクリーム色や薄い黄色のものに変えるだけで、文字が読みやすくなることがあります。
また、パソコンやタブレットで学習する際は、背景色を白から少しグレーがかった色やセピア色に設定するのも良い方法です.
どの色の組み合わせが読みやすいかは個人差が大きいので、子どもと一緒に「どの色が見やすい?」と相談しながら、最適なものを見つけてあげてください。
読み上げ(音声読み上げ)機能を活用する
文字を読むことに困難がある場合、耳から情報を入れることで学習の負担を大きく減らすことができます。
スマートフォンやタブレット、パソコンには、画面に表示された文字を音声で読み上げてくれる「読み上げ(Text-to-Speech)」機能が標準で搭載されています。
この機能を活用すれば、国語の教科書や物語の本などを、まるでオーディオブックのように聞くことが可能です。
文字を読むことへの抵抗感が強い子どもでも、耳からならすんなりと物語の世界に入っていけるかもしれません。
最初は操作に戸惑うかもしれませんが、慣れれば宿題の長文読解などにも活用でき、学習の可能性を大きく広げてくれる心強い味方になります。
リーディングルーラーやカラーシートを活用する
文章のどこを読んでいるかわからなくなってしまう、行を飛ばしてしまうという子どもには、「リーディングルーラー」や「カラーシート」が役立ちます。
リーディングルーラーは、読む行だけを切り抜いた定規のようなツールで、他の行を隠すことで、今読んでいる場所に集中しやすくしてくれます。
また、カラーシートは透明な色のついた下敷きのようなもので、紙の上に重ねることで文字と背景のコントラストを和らげ、眩しさを軽減する効果があります。
これらのツールは、文房具店やオンラインストアで手軽に購入でき、厚紙や色のついたクリアファイルなどで自作することも可能です。
子どもが「これなら読みやすい!」と感じるお気に入りの道具を見つけることで、読書への苦手意識を和らげるきっかけになるでしょう。
音声入力で「書く」をサポートする
文字を書くことに強い負担を感じるディスグラフィアの子どもには、「音声入力」機能が大きな助けとなります。
これは、話した言葉を自動で文字に変換してくれる機能で、スマートフォンやパソコンに標準で備わっています。
例えば、作文や日記の宿題で「何を書くか」は思いついているのに、「文字を書く」という作業が大きな壁となって進まないことがあります。
そんな時、音声入力を使えば、書くことのストレスから解放され、自分の考えやアイデアをスムーズに表現できます。
まずは音声入力で文章の骨子を作り、その後に手で清書するというステップを踏むのも良いでしょう。
「書くこと=つらいこと」というイメージを、「伝えること=楽しいこと」に変えていくための有効なツールです。
学習方法を工夫する
毎日の学習方法を少し工夫するだけで、子どもの負担を減らし、「できた!」という成功体験を増やすことができます。
大切なのは、一度にたくさんの情報を与えすぎない「スモールステップ」です。
例えば、漢字練習なら一度に10個覚えるのではなく、「今日はこの2つだけ完璧にしよう」と目標を小さく設定します。
また、学習に様々な感覚を取り入れるのも効果的です。
指でなぞりながら漢字を覚えたり、計算問題を声に出して解いたりすることで、視覚だけでなく触覚や聴覚も使い、記憶に残りやすくなります。
「勉強」と構えるのではなく、カルタやしりとりのようなゲーム形式で文字に触れる機会を作るのも良いでしょう。
楽しさを感じることが、学習へのモチベーションにつながります。
保護者が大切にしたい3つのこと

結果ではなく「努力」をほめる(「頑張って読もうとしたね」)
子どもがテストで良い点を取ったり、宿題を完璧にこなしたりした時だけほめるのではありません。
大切なのは、結果に至るまでのプロセス、つまり「努力」そのものに目を向けて、具体的にほめてあげることです。
例えば、音読が途中でつっかえてしまっても、「最後まで諦めずに読もうとしたね、すごいよ」と声をかけます。
漢字テストの点数が悪くても、「昨日、一生懸命練習していたのを知っているよ」と伝えてあげてください。
結果がどうであれ、自分のがんばりを一番近くで見ていてくれる、認めてくれる存在がいるという安心感が、子どもの「次もやってみよう」という意欲を育んでいきます。
「できたこと」「得意なこと」に目を向け、自信を育む
学習障害の特性があると、どうしても「できないこと」にばかり目が向きがちになります。
しかし、子どもには必ず「できること」や「得意なこと」があるはずです。
それは、絵を描くことかもしれませんし、運動能力や、誰にでも優しくできることかもしれません。
読み書きが苦手でも、驚くほどユニークな発想力を持っている子もいます。
「苦手なこと」を克服させようと躍起になるのではなく、子どもの「得意なこと」を存分に伸ばしてあげましょう。
そこで得た自信は、「苦手なことにも挑戦してみようかな」というエネルギーに必ずつながります。
「あなたにはこんなに素敵なところがある」というメッセージを伝え続けることが、何よりのサポートになります。
他人と比べず、その子自身のペースと成長を見守る
「〇〇ちゃんはもう漢字が書けるのに」「クラスのみんなはスラスラ読めるのに」と、周りの子と比べてあせってしまう気持ちは、親として自然なことです。
しかし、そのあせりは子どもにとって大きなプレッシャーになってしまいます。
比べるべき相手は、周りの子どもたちではなく、「昨日の子ども自身」です。
昨日よりも一行多く本が読めた、先週は書けなかった文字が一つ書けた。
そのような小さな成長を見つけて、一緒に喜んであげてください。
発達のペースは一人ひとり全く違います。
子ども自身のペースを尊重し、「あなたのままでいいんだよ」という安心感を与えてあげることが、子どもが自分らしく伸びていくための土台となるのです。
一人で抱え込まないで!専門機関への相談という選択肢

学校の担任、スクールカウンセラー
「もしかして…」と感じたら、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが大切です。
専門家に相談することは、特別なことではありません。
まず一番身近な相談相手は、学校の担任の先生や、学校に常駐しているスクールカウンセラーです。
日頃の子どもの様子を一番よく知っているため、学校での具体的な状況を共有し、協力体制を築くことができます。
合理的配慮(個々の特性に合わせた学習環境の調整)について相談したり、専門機関へのつなぎ役になってもらったりすることも可能です。
まずは連絡帳や個人面談の機会に、「読み書きで少し心配なことがありまして」と切り出してみてください。
市町村の教育センター、子育て支援センター
お住まいの市町村には、教育に関する相談を受け付ける「教育センター(教育支援センター)」や、子育て全般の悩みに対応する「子育て支援センター」が設置されています。
これらの機関では、専門の相談員や心理士が話を聞いてくれ、必要に応じて発達検査の実施や、より専門的な機関を紹介してくれます。
公的な機関なので、無料で相談できる場合がほとんどです。
「どこに相談していいかわからない」という最初のステップとして、非常に頼りになる存在です。
かかりつけの小児科、児童精神科などの医療機関
学習面の困難さだけでなく、不登校や心身の不調など、他の心配事も見られる場合は、医療機関への相談も選択肢の一つです。
かかりつけの小児科医に相談すれば、地域の専門医を紹介してくれることがあります。
また、児童精神科や発達外来などでは、医師による診察や心理士による詳しい検査を通じて、学習障害の診断を受けることが可能です。
診断がつくことで、子ども自身が自分の特性を理解し、受け入れるきっかけになる場合もあります。
発達障害者支援センター
各都道府県や指定都市に設置されている「発達障害者支援センター」は、発達障害に関する総合的な相談窓口です。
本人や家族からの相談に応じて、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携しながら、一人ひとりに合った支援計画を立てる手助けをしてくれます。
乳幼児期から成人期まで、ライフステージを通じた一貫したサポートを受けられるのが大きな特徴です。
子どもの将来を見据えた、長期的なサポートについて相談したい場合に心強い味方となってくれるでしょう。
まとめ
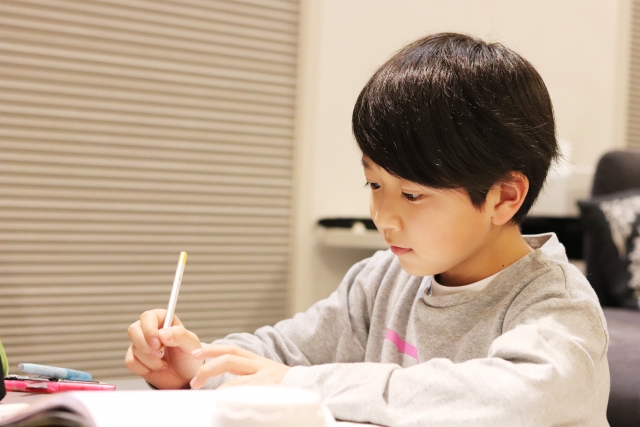
この記事では、学習障害のある子どもの文字の見え方や、家庭でできるサポート方法について詳しく解説してきました。
子どもの「見えにくさ」を理解することは、不安な気持ちを和らげ、的確なサポートを始めるためのスタートラインです。
「どうしてうちの子だけ」と一人で悩まず、学校や専門家など、頼れる存在はたくさんあります。
この記事が、あなたの踏み出す一歩を、そっと後押しできれば嬉しく思います。
子どもの可能性を信じて、その子らしいペースで共に歩んでいきましょう。




