
「教室で落ち着いて座っていられない」
「忘れ物が多くて困る」
ADHDのお子さんを育てる中で、このような悩みを抱えている親御さんは多いのではないでしょうか。ADHDは子どもの発達段階によって様々な形で現れる特性です。
お子さんの行動の背景にある特性を理解し、適切な支援を行うことで、子どもたちは確実に成長していきます。ADHDの特性を持つ子どもたちの可能性を伸ばすために、具体的な関わり方や支援の方法を知ることが大切です。
この記事では、ADHDの基本的な特徴から、年齢に応じた育てにくさの具体例、効果的な支援方法まで、実践的な情報を紹介します。お子さんとの関わり方に悩む親御さんの力になれる情報を、わかりやすく解説していきます。
ADHD(注意欠如多動症)とは何か
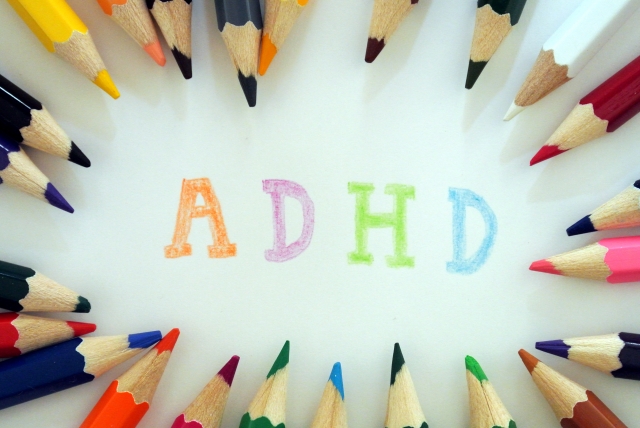
ADHD(注意欠如多動症)は、年齢や発達段階に不釣り合いな注意力の困難さや多動性、衝動性を特徴とする発達障害の一つです。この症状は12歳以前から現れ始め、学校や家庭など複数の場面で日常生活に影響を及ぼします。
ADHDの原因は、生まれつきの脳の発達の偏りによるものと考えられています。育て方やしつけの問題ではなく、脳内の神経伝達物質の働きに関係があることが研究でわかってきました。このことを理解することは、子どもへの適切な支援を考える上で重要です。
ADHDの主な特徴

3つの行動特性がある
ADHDには独特な行動特性があり、これらの特性は子どもの日常生活や学習に大きな影響を与えます。これらの特性は単独で現れることもあれば、複数の特性が組み合わさって現れることもあります。
ADHDの特性は「不注意」「多動性」「衝動性」の3つです。不注意優勢型は女性に多く、多動性・衝動性優勢型は男性に多い傾向があります。両方の特性を持った混合型は全体の約8割を占め、最も一般的なタイプとされています。
不注意の特徴
不注意の特徴を持つ子どもは、日常生活のさまざまな場面で困難を感じやすい傾向があります。学校の課題や遊びの最中でも集中力が持続せず、すぐに気が散ってしまうことが特徴的です。
特に目立つのが、忘れ物や物をなくすことの多さです。学校に持っていく物や家に持ち帰る物を忘れ、宿題や約束事も頭から抜け落ちてしまいます。持ち物の管理が苦手で、物を置いた場所を覚えていられないことも珍しくありません。
整理整頓も大きな課題となります。部屋やデスクの上が散らかりやすく、片付けを始めても途中で別のことに気を取られて投げ出してしまいがちです。物を探すときは全部ひっくり返してしまい、さらに散らかってしまう悪循環に陥ることもあります。
また、指示された内容を理解し、順序立てて物事を進めることも困難です。計画を立てたり、段取りよく行動したりすることができず、課題を最後までやり遂げられないことが多くなります。このような特性は、学業面だけでなく、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼすことがあります。
多動性の特徴
多動性のある子どもは、まるで体の中にエンジンが入っているかのように、常に体を動かしている状態が特徴的です。椅子に座っているときでも、手足をバタバタと動かしたり、体を前後に揺らしたりして、じっとしていることが困難です。
特に授業中や食事中など、静かに座っていなければならない場面で、突然立ち上がって歩き回ったり、教室や食堂を走り回ったりすることがあります。このような行動は本人の意思でコントロールすることが難しく、不適切な状況でも衝動的に体を動かしてしまいます。
また、遊びの場面でも静かに取り組むことが苦手で、常に体を動かしながら活動する傾向があります。公園や遊び場では、順番を待つことができずに走り回ったり、遊具に激しく上り下りしたりすることも多くみられます。
衝動性の特徴
衝動性のある子どもは、思いついたことをすぐに行動に移してしまう特徴があります。考えてから行動することが難しく、突発的な行動が目立ちます。例えば、許可を得ずに他人の物を使ったり、危険な場所に突然走り出したりすることがあります。
会話の場面では、他の人が話している最中でも自分の考えを我慢できずに口をはさんでしまいます。特に、静かにしていなければならない場面でも、話し続けてしまう傾向があります。また、列に並んで順番を待つことも苦手で、自分の番が来る前に割り込んでしまうことも珍しくありません。
感情のコントロールも難しく、思い通りにならないことがあるとすぐにイライラして感情的になります。その結果、大声を出したり、物に当たったりする行動につながることがあります。特に、欲しいものを目にした時は、後先を考えずに衝動買いをしてしまうなど、自分の欲求を抑えることが困難です。
ADHDを持つ子どもの育てにくさの具体例

乳幼児期の特徴
乳幼児期のADHDの特徴は、発達段階によって異なる形で現れます。乳児期には「寝つきが悪い」「視線を合わせにくい」「抱っこを嫌がる」といった特徴が見られることがありますが、これらの特徴だけでADHDと診断することはできません。
ADHDの特性が明確になり始めるのは早くても2歳頃からです。この時期になると、落ち着きのなさや衝動的な行動が目立ち始め、「じっとしていられない」「かんしゃくを起こすことが多い」「物を壊したり乱暴な遊びを好む」などの様子が見られるようになります。
特に幼児期(2〜5歳)では、多動性と衝動性の症状が顕著になります。常に体を動かし続ける、他の子どものおもちゃを突然奪う、危険な場所へ突然走り出すなどの行動が見られます。また、公共の場所でも落ち着きがなく、電車やバスの中で騒いでしまうことも多くなります。
この時期のADHDの特性は、発達とともに改善していく可能性もあり、また自閉スペクトラム症などの別の発達障害の一側面である可能性もあります。そのため、乳幼児期での診断は慎重に行う必要があり、薬物療法もあまり行われません。まずは様子を見守りながら、専門家に相談することが推奨されています。
日常生活での困難
ADHDの子どもは、日常生活の様々な場面で困難が生じやすい傾向があります。特に目立つのが、整理整頓の苦手さです。部屋の中におもちゃや持ち物が散らかりっぱなしになり、片付けを始めても途中で別のことに気を取られて投げ出してしまいがちです。
スケジュールを立てることが難しく、約束の時間に遅れたり、やるべき活動を忘れたりすることが頻繁に起こります。特に本人の見積もる時間と実際にかかる時間との間にズレが生じやすく、予定通りに物事を進められないことが多くなります。
日常的なタスクを先延ばしにする傾向も特徴的です。家事や身の回りの整理などを後回しにしがちで、その結果として生活リズムが乱れやすくなります。一度乱れた生活リズムを立て直すことも難しく、悪循環に陥ることがあります。
学習面での課題
ADHDのある子どもは、学習面で様々な困難を抱えることが多くあります。授業への集中力が散漫で、先生の話を最後まで聞くことができず、授業の内容を十分に理解できないことがあります。
計画を立てて学習を進めることが苦手で、期限を守れないことが頻繁に起こります。忘れ物が多く、必要な教材を持ってこないために授業に参加できないこともあるでしょう。このような状況が続くと、学業成績に大きな影響が出てしまいます。
さらに、先生からの指示内容を正確に理解し、記憶することも難しい傾向があります。特に口頭での複雑な指示は、聞いた内容を覚えていられないことが多く、結果として必要な学習活動に参加できないことがあります。このような特性は、本人の努力不足ではなく、ADHDの特性によるものであることを理解することが重要です。
身体面の困難
ADHDのある子どもは、身体面でも特徴的な困りごとを抱えていることがあります。
まず、感覚の特異性です。音や光、触れられることに対して必要以上に敏感に反応したり、逆に痛みや暑さ・寒さをあまり感じなかったりすることがあります。
常に体を動かしていたい気持ちが強いため、疲れやすく体力を消耗しやすい傾向があります。特に授業中など、じっとしていることを求められる場面では、体を揺らしたり手足を動かしたりすることで余分なエネルギーを使ってしまい、一日の終わりには想像以上の疲れが出ることがあります。
また、手先の不器用さも特徴の一つです。はさみ、箸、鉛筆などの道具をうまく使えないことが多く、これは脳の前頭葉における運動の計画や実行機能の特性が関係していると考えられています。
衝動性と感覚の特異性が重なることで起こる危険な行動にも注意が必要です。高いところから突然飛び降りたり、道路に飛び出したりすることがあり、特に痛みを感じにくい場合は怪我の発見が遅れる可能性があります。
これらの特徴は個々に異なるので、子どもの様子をよく観察し、必要に応じて環境調整や専門家への相談を検討しましょう。
ADHDの子どもとの向き合い方

できることに着目する
ADHDのある子どもは、できないことを指摘されることが多く、自己肯定感が低下しがちです。しかし、自分の興味のある分野や好きなことに対しては驚くほどの集中力を発揮し、優れた能力を見せることがあります。そのため、子どもの得意分野や強みに着目し、それを伸ばしていく支援が重要です。
子どもの行動を観察する際は、できないことではなく、できていることに注目します。例えば、「宿題を5分間集中して取り組めた」「おもちゃを決められた場所に片付けられた」など、具体的な行動を見つけて即座にほめることで、子どもは自信を持つことができるでしょう。
特に、ADHDの子どもは一つのことに深く没頭する特性があり、その分野では人一倍の知識や技能を身につけることができます。この特性を活かし、子どもが興味を持つ活動や学びの機会を積極的に提供することで、その分野での専門性を高めることが可能です。
また、できたことを具体的にほめることで、子どもは「自分にもできる」という実感を持ち、新しいことにチャレンジする意欲が生まれます。小さな成功体験を重ねることで、子どもは徐々に自信を持ち、前向きな態度で物事に取り組めるようになっていきます。
日常生活のスケジュールを決める
ADHDのある子どもにとって、時間の管理や予定の把握は大きな課題となります。一日の生活リズムを整えるためには、明確なスケジュールを設定することが効果的です。
スケジュール作成の基本的なポイント:
- 毎日の基本的な活動(起床、食事、学習、就寝など)は、できるだけ同じ時間帯に設定する
- 活動と活動の間に、適度な休憩時間を入れる
- 子どもが見通しを持ちやすいよう、一日の大まかな流れを固定する
- 一つの活動の時間は子どもの集中力に合わせて設定する(例:学習時間は20-30分程度)
- 予定変更の可能性がある場合は、あらかじめ「予備の予定」を準備しておく
子どもの様子を見ながら、無理のない範囲でスケジュールを調整していくのがポイントです。急な変更は子どもの不安やパニックを引き起こす可能性があるため、変更が必要な場合は早めに伝えることを心がけましょう。
適度に体を動かすようにする
ADHDのある子どもには、適度な運動を取り入れることで症状が改善する効果が期待できます。特に散歩、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、脳に酸素が十分に行き渡ることで集中力が高まり、落ち着きのなさや衝動的な行動が落ち着いてくる傾向があります。
運動には脳内の神経伝達物質のバランスを整える効果があり、特に前頭前野が活性化されることで、注意力や行動のコントロール力が向上します。効果的な運動時間は1日20〜30分程度を目安とし、特に朝の運動は一日の集中力を保つのに役立ちます。
運動の選び方のポイントは次のとおりです。
- 子どもの好みや年齢に合わせて選ぶ
- 一人で行う運動(水泳、ランニング)や集団での運動(チームスポーツ)を組み合わせる
- 最初は短い時間から始めて、徐々に時間を延ばしていく
- 親子で一緒に体を動かすことで、コミュニケーションの機会にもする
このような運動習慣を通じて、達成感や自信を育むとともに、友だちとの関わりも自然と増やしていくことができます。
守りやすい具体的なルールを設定する
ADHDのある子どもにとって、分かりやすく守りやすいルール設定は、日常生活を安定させる重要な要素です。ルールを設定する際は、シンプルで具体的な内容にすることが大切です。例えば、「きちんとする」という抽象的な表現ではなく、「おもちゃは遊んだ後に箱に入れる」というように、具体的な行動を示します。
ルールは一度に多く設定せず、最初は2〜3個程度の重要なものから始めます。また、ルールを視覚的に示すことも効果的です。カレンダーやホワイトボードにルールを書いて壁に貼ったり、絵カードを使って表示したりすることで、子どもは常にルールを確認することができます。
特に重要なのは、ルールを守れたときの肯定的な評価です。小さな成功でも必ずほめ、達成感を感じられるようにします。ほめる回数は注意する回数の10倍以上を目安にすることで、子どもの自信と意欲を育てることができます。
叱らずに行動を見守る
ADHDのある子どもへの接し方で最も大切なのは、まず子どもの行動を理解しようとする姿勢です。子どもが気になる行動をとった時は、すぐに叱るのではなく、なぜそのような行動をとったのか、背景にある理由を理解するように心がけましょう。
見守る際の具体的なポイントは次のとおりです。
- 行動だけに注目し、子どもの人格を否定するような言葉は使わない
- 「あなたはいつもこうだから」といった決めつけを避ける
- 子どもが興奮している時は、むやみに止めようとせず、落ち着くのを待つ
- 必要に応じて、静かな別室など、気持ちを落ち着かせられる場所を用意する
できた行動は具体的に認めることで、子どもは自信を持ち、これからも頑張ろうという気持ちが芽生えます。「片付けを最後まで頑張ったね」「お友だちと順番を守って遊べたね」など、具体的な行動をほめることを心がけましょう。
ADHDの子どもとのコミュニケーションの取り方

視覚的な情報を使う
ADHDのある子どもは、目で見える形で示された情報を理解することが得意です。口頭での説明だけでは情報が消えてしまい理解が難しい一方で、視覚的な情報は脳に保管しやすく、行動に移しやすい特徴があります。
視覚的なコミュニケーションの取り方の例を紹介します。
絵カードやイラストの活用
- 背景などの余計な情報がないシンプルな絵や写真を使う
- 「おもちゃを片付ける」など、具体的な行動を一枚のカードで示す
- 文字だけでなく、ピクトグラムなども組み合わせる
時間の経過を視覚化
- デジタルタイマーやアナログ時計を使って残り時間を示す
- 「あと10分」という言葉だけでなく、実際に時間が減っていく様子を見せる
情報の構造化
- 「左から右」「上から下」という一定のルールで情報を並べる
- 終わった活動のカードを外したり、チェックを入れたりして達成感を持てるようにする
- 子どもの理解力に合わせて、表示方法を工夫する
このような視覚的なサポートを活用することで、子どもは自分で見通しを持って行動できるようになり、自主性も育まれていくでしょう。
指示は具体的に一つずつ伝える
ADHDのある子どもに指示を出す際は、具体的で分かりやすい伝え方を心がけることが重要です。「ちゃんとして」「急いで」といった抽象的な表現は避け、「椅子に座って、目を見て話を聞いてね」のように、具体的な行動を示して伝えましょう。
指示を出す前には、必ず子どもの注意を引くことが大切です。子どもの正面に立ち、目を合わせてから、穏やかな声で話しかけるのがポイントです。
複数の指示を一度に出すと、子どもは混乱してしまい、何から手をつければよいか分からなくなります。例えば、「宿題をして、部屋を片付けて、お風呂に入って」と一度に伝えるのではなく、「まずは宿題を終わらせよう」と一つずつ指示を出し、その行動が完了してから次の指示を出すようにします。
また、マナーや規則を伝える際も、抽象的な言い方は避けましょう。「マナーを守りなさい」ではなく、「お友達の話は最後まで聞いてから、手を挙げて発言してね」というように、具体的な行動レベルで伝えることで、子どもは何をすればよいのかを理解しやすくなります。
感情的にならず、穏やかな声で話しかける
コミュニケーションの取り方には、具体的な技術があります。話しかける際は「穏やかに」「近くに寄って」「静かな声で」という3つのポイント(CCQ:Calm, Close, Quiet)を意識しましょう。
効果的なコミュニケーションの方法をいくつか紹介します。
- 子どもの正面に立ち、目を合わせてから話を始める
- 後ろからや見えない場所からの声かけは避ける
- 「ダメ」「やめなさい」という否定的な表現ではなく、「こうしてみよう」「次はこうしたらいいね」という建設的な言葉を使う
- 子どもの気持ちに共感する言葉を使う(「難しいと感じているんだね」「困っているんだね」)
- その上で「一緒に考えてみようか」など、解決に向けた声かけをする
日々の会話の中で大切なのは、子どもの小さな変化や成長に気づいたら、すぐに具体的な言葉で伝えることです。子どもとの信頼関係を築くためには、こうした肯定的なコミュニケーションの積み重ねが重要です。
まとめ

ADHDは、不注意、多動性、衝動性という特徴を持つ発達障害です。症状は子どもの年齢や発達段階によって様々な形で現れ、日常生活や学習面において独特の困難さをもたらすことがあります。
しかし、適切な理解と支援があれば、子どもたちは自分らしい方法で成長していくことができます。今回紹介したような支援方法を組み合わせることで、子どもの生活はより安定したものとなっていきます。
何より大切なのは、叱ることではなく、子どもの行動を理解しようとする姿勢です。できないことを責めるのではなく、できることに着目し、スモールステップで成長を支えていくことで、子どもは自信を持って新しいことにチャレンジできるようになるでしょう。




