
ADHDのお子さんの前頭葉トレーニング、どのように進めればよいのか悩んでいませんか?
集中力を高める方法を探しているけれど、具体的な実践方法がわからない、という方も多いのではないでしょうか。
ADHDのお子さんの場合、前頭葉の発達に特徴があり、適切なトレーニングを行うことで集中力や実行機能を向上させることができます。家庭でできる効果的なトレーニング方法も数多く存在します。
この記事では、ADHDのお子さんをお持ちの方に向けて、年齢別の前頭葉トレーニング方法や、日常生活で実践できる具体的な取り組みについて解説します。お子さんの成長をサポートする参考として、ぜひ最後までお読みください。
ADHDの子どもの前頭葉の発達
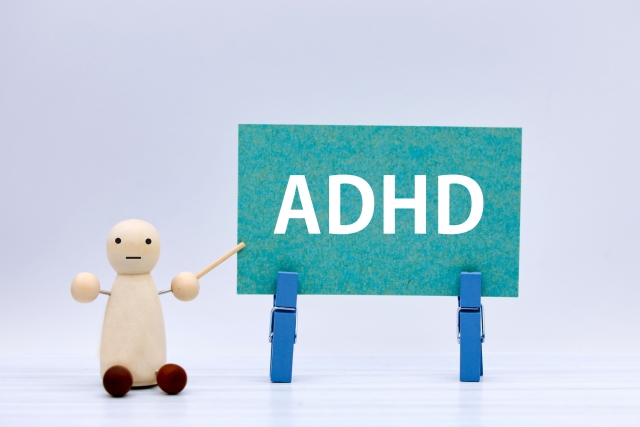
ADHDと前頭葉の機能低下の関係
ADHDの子どもは、注意が続かなかったり、衝動的に行動してしまったりすることがあります。その背景には、前頭葉が抑制や計画を担う機能をうまく発揮できないケースがあるのです。
脳の中でも前頭葉は、行動をコントロールする指令塔のような役割を持ちます。
発達が遅れたり機能が低下していると、やるべき作業に集中できなくなるほか、感情を落ち着かせるのも難しくなりがちです。
たとえば、授業中は注意散漫で落ち着きを欠く一方、自分の好きなことにはエネルギーを注ぎ込みすぎてしまうなど、極端にムラがある行動パターンが見られる場合があります。
加えて、この衝動性や不注意は家庭でも影響を及ぼします。
些細なことでかんしゃくを起こしたり、楽しいこと以外は途中で投げ出してしまったりと、家族の日常が混乱しやすくなることもあるでしょう。
前頭葉の働きが不十分だと、意識して「今は我慢しよう」と思っても感情を制御しにくいため、思わぬトラブルに発展することがあります。
しかし、脳は環境やトレーニングの影響を受けて変化しやすい面があります。生活リズムの見直しや遊び、運動といった身近な工夫からでも、前頭葉の機能を徐々にサポートできる可能性があるのです。早期にアプローチを始めると、その後の学習や社会生活で活きるメリットも大きくなります。
ADHDの子どもが前頭葉を鍛えるメリット
前頭葉を意識的に鍛えることで、まず期待できるのが集中力の向上です。衝動的な行動や不注意が多い子どもでも、前頭葉の機能を徐々に伸ばしていくことで、落ち着いて行動できる時間が増えていきます。これは宿題や学習の定着率を上げるだけでなく、自己肯定感を高めるうえでも非常に重要な要素です。
鍛える方法としては、認知トレーニングや運動、ゲームを活用したアプローチなど、家庭や専門家のもとで実践できる多彩な手段があります。
こうしたトレーニングを継続すると、集中力が高まり、宿題に取り組む際の時間や効率がアップするだけでなく、衝動的な行動が減り、イライラしやすい場面でも落ち着いて行動できるようになる子どもが多く見られます。
さらに、感情のコントロールがスムーズになれば、自分への自信が高まるだけでなく、周囲からの評価も向上する傾向があります。「落ち着いてやり遂げられた」という成功体験の積み重ねはモチベーションの維持に直結し、習い事や学校活動にも前向きに取り組めるようになるのです。
大人や先生も子どもの変化に気づきやすくなるため、ほめる機会が自然と増え、結果として親子関係や学校での人間関係が良好になるという好循環が生まれます。
このように、前頭葉を鍛えることは日常生活の安定だけでなく、子どもの未来を明るく広げる可能性を秘めています。ただし、効果が現れるまでには個人差があり、焦って結果を求めてしまうと子どもがストレスを感じる原因になるかもしれません。
家族が前向きにサポートを続け、子ども自身も無理のないペースで取り組めるよう配慮していくことが大切です。
ADHDの子どもの前頭葉を鍛えるトレーニング方法

認知トレーニング
認知トレーニングは、脳の注意力や記憶力、判断力などをピンポイントで鍛える方法です。ゲーム感覚で課題を解くソフトウェアやアプリを活用して、短時間でも集中して取り組む機会をつくります。
視覚や聴覚への刺激を組み合わせることで、子どもの脳内の情報処理が活性化されやすくなるのがポイントです。
代表的なトレーニングには以下のようなものがあります。
- 数字や図形を覚えて回答する課題
- パズルや図形認知ソフトを使ったプログラム
- カードゲーム(神経衰弱など)や数当てゲーム
これらのトレーニングは、子どもが「面白い」「もう一回やりたい」と感じやすく、飽きにくいという特長があります。ただし、難易度が高すぎると投げ出してしまうことがあるため、少しずつステップアップしていくのが効果的です。
認知トレーニングを継続すると次のようなメリットが期待できます。
- 「集中を維持する力」が身につきやすい
- 「情報を効率的に処理する力」が向上する
- 専門家や教師と相談しながらカリキュラムを組むと、子どものやる気を引き出しやすい
最終的には、宿題や学校生活で必要な注意力や作業記憶の強化につながり、「自分にもできるかも」と思える自己肯定感を育む大きな一歩となるでしょう。
運動や遊びを通じたトレーニング
運動や遊びを通じたアプローチは、前頭葉を刺激すると同時に体を動かせる点が魅力です。バランスボールや縄跳び、簡単なダンスなどの有酸素運動は、脳に酸素を十分に送り、集中力を高めやすくします。
キャッチボールやサッカーなどのチームスポーツでは、仲間とのルール共有やコミュニケーションを通じて、注意力や協調性が自然に身につきやすくなります。
取り入れやすい運動・遊びの例は次のとおりです。
- ボードゲームやパズル:問題解決・判断力のトレーニング
- ごっこ遊び:役割を演じながら想像力と行動コントロールを育む
- 音楽活動:楽器演奏やダンスを通じてリズム感と注意力を同時に鍛える
遊びを取り入れる場合は、ルールのあるボードゲームやパズルを使うと、問題解決や判断力を培う練習になります。ごっこ遊びのように、役割を演じながら状況を理解する遊びもおすすめです。
子どもは自然にシミュレーション力を養い、行動をコントロールする練習を重ねます。
また、こうした遊びには、楽しみながら取り組みやすいというメリットがあります。体を動かしてストレスを発散できるため、気持ちの切り替えもしやすくなります。遊びの中で「考えて動く」習慣が身につけば、前頭葉が担う行動制御の機能が刺激され、集中して行動する力が少しずつ高まっていくでしょう。
日常生活で行うトレーニング
日常生活をトレーニングの場に変える工夫は、最も手軽に取り組めて効果が長続きする方法です。朝起きたら決まった順序で身支度をする、時間を計って宿題を進めるなど、ルーティン化と時間管理を意識する習慣づくりがポイントです。
計画通りに進める練習を重ねることで、前頭葉が求める秩序感や自制心を自然に育みやすくなります。
日常生活に取り入れたい工夫の例をいくつか紹介します。ぜひ意識してみてください。
お手伝い
- 料理、洗濯、掃除など、手順を踏んで行う家事は前頭葉の良い訓練になる
- 料理なら材料を用意し、手順を考え、火加減を調整するなど多角的な認知機能を活用できる
時間管理
- タイマーを使い、宿題や準備にかかる時間を計る
- どの作業をどれくらいの時間で終わらせるか、子どもと一緒に考える
睡眠と食事
- 規則正しい睡眠リズムを保ち、集中力アップを図る
- 脳に必要な栄養を供給することで、学習意欲を維持しやすくなる
複数のステップがある家事を手伝わせると、子どもは「何から始めるか」「次にやることは何か」を意識するようになります。これが前頭葉を使う良い練習になり、段取り力や集中力を育むのに効果的です。
こうした日々の小さな習慣の積み重ねが、子どもの前頭葉の機能をサポートし、学校や家庭でより落ち着いた行動や確実な作業遂行を実現する基礎になります。
(年齢別)ADHDの子どもに効果的なトレーニング方法

幼児期(0~6歳)
幼児期は脳の可塑性が高く、遊びを通じて五感をまんべんなく刺激しやすい時期です。粘土や積み木のように手先を使う遊びや、砂場遊び、リズム運動など、多様な体験を通じて脳全体を発達させやすい特徴があります。興味や関心を引く活動が多いほど、子どもは集中して取り組みやすくなるでしょう。
次のような五感を刺激する遊びを取り入れてみましょう。
- 粘土や積み木:手先を使うことで計画性や観察力をはぐくむ
- 砂場遊び:さまざまな感触を体験し、脳を刺激
- 外遊び:公園で走り回ったり、遊具を使ってバランス感覚を養う
まずは体を思いきり動かす運動系の遊びが有効です。たとえば、縄跳びやボール投げでは、タイミングやバランス感覚を意識しながら動く練習になります。
絵本の読み聞かせやリズム遊びも、幼児期には有効なアプローチです。読み終わった後に子どもと一緒に感想を言い合えば、想像力だけでなくコミュニケーション力や表現力も育ちやすくなります。
また、リズム遊びでは音楽に合わせて手をたたいたり踊ったりするうちに、自己表現と注意力が並行して鍛えられます。幼児期はまだ集中時間が短いので、無理をさせず楽しくできる範囲で取り組みを継続することが大切です。
小学生(7~12歳)
小学生になると、学習の基礎として読む・書く・計算する力を育てながら、さまざまな課外活動や友人関係を経験していきます。この時期に前頭葉を鍛えておくと、学習だけでなく社会性や協調性にも好影響が期待できます。
小学生は「認知トレーニング」「運動」「日常生活のルーティン化」の3方向のトレーニングがおすすめです。
認知トレーニング
- パズルやカードゲーム:ルールを理解して遊ぶことで思考力をアップ
- 音読や計算問題:ワーキングメモリや処理速度を鍛える
運動
- キャッチボールやチームスポーツ:仲間と連携して動くことで注意力と協調性を育む
- リズム運動(ダンス、音楽):リズム感を養いつつ、前頭葉を刺激
日常生活のルーティン化
- 朝の支度や帰宅後の流れを明確にして、子どもが自分で管理できるようにする
- タイマーを使って宿題や家事を行い、時間配分を意識させる
小学生はまだ遊び心が旺盛で、飽きっぽい一面もあります。ゲーム感覚や競争要素を取り入れるなど、楽しく続けられる工夫を凝らすと効果的です。また、子どもが得意と感じる領域を見つけ、そこを伸ばしてあげると自信につながり、前頭葉トレーニングのモチベーションも高めやすくなります。
中学・高校生(13~18歳)
中学・高校生になると、学習内容が高度化し、部活動やアルバイトなど外部との関わりも活発になってきます。自己管理や時間管理の必要性が飛躍的に増す時期ですが、同時に思春期特有のストレスや不安も抱えやすくなるため、前頭葉が整っているかどうかがより重要になります。
中学・高校生に向いているトレーニングの例は次のとおりです。
自己管理能力の強化
- スケジュール帳やタスク管理アプリを使い、勉強や日々の予定を可視化する
- 模擬試験や定期テストを分析し、弱点分野に集中して学習するなど、計画を立てて実行する流れを習慣化する
応用力や社会性を磨く活動
- ボランティアや地域活動への参加:責任感とコミュニケーション力を養う
- プレゼンテーションやディベート:論理的思考力と表現力を高める
運動や部活動
- 自分の役割を理解し、チームの動きを把握することで臨機応変な判断力を身につける
- 適度な運動は情緒の安定や気分転換にもつながり、集中力が乱れやすい思春期を乗り越えやすくする
この時期は自分の将来を考えるうえで大切な時期でもあるため、「今のうちにトレーニングを続けておくと、将来の目標に近づける」という具体的なビジョンを示すと、子どものやる気を引き出しやすくなります。
また、本人が主体的に計画を立てて実行できるよう、必要に応じて大人がアドバイスをする体制を整えることで、前頭葉の機能をさらに伸ばせる可能性が高まるでしょう。
トレーニング方法を行う上での注意点

子どもの発達段階に合わせたトレーニングを選ぶ
発達段階によって、取り組めるタスクや理解できるルールは大きく異なります。幼児期は遊びを通して五感を刺激し、簡単な動作やルールを学ぶところから始めると効果的です。
小学生以降になると、少し複雑なパズルやカードゲーム、計画的にタスクをこなす練習などに挑戦できます。中学・高校生では自己管理力が求められる場面が増えるため、スケジュール帳やタスク管理アプリを利用して、継続的に運用する習慣を身につけましょう。
こうした工夫を年齢や個人差に合わせて最適化することで、前頭葉を刺激しながらスムーズにトレーニングを進めることができます。
無理強いはしない
子どもは自分が嫌だと感じることを長く続けるのが難しいものです。嫌々取り組むと集中力が続かず、脳に必要な学びの刺激を与えにくくなります。
特にADHD傾向のある子どもは、ストレスがかかったり、指示が過剰になったりするとモチベーションが大きく下がってしまうこともあるでしょう。
そのため、子どもが前向きに取り組める難易度や課題の量からスタートし、成功体験を得られるように配慮することが大切です。小さな達成感を積み重ねることで、「もう少しやってみよう」という意欲が育まれやすくなります。
集中しやすい環境を整える
集中を促すうえで、周囲の環境づくりは欠かせません。テレビやスマートフォンなど、強い刺激を発するものが近くにあると、子どもの意識がそちらへ向かいやすくなります。
学習やトレーニングの時間は、なるべくそういったアイテムを別の部屋に置いておくなど、注意をそらす要因を取り除きましょう。BGMを流す場合は、歌詞のない静かな曲を選ぶなど、極力集中を妨げないような環境を心がけるのもポイントです。
また、机や椅子の高さ、照明の明るさなど、子どもが心地よく集中できる条件を整えることも大切です。自分専用のスペースを用意できるなら、そこで落ち着いて勉強やトレーニングをする習慣をつけるとよいでしょう。
ほめて伸ばす声かけをする
子どもはほめられることで自信をつけ、やる気を継続しやすくなります。ADHDの子どもは失敗や注意を受ける機会が多く、自己肯定感が下がりがちです。
わずかな進歩でも「よくがんばったね」「ここが上手になったね」と具体的にほめると、達成感を抱きやすくなります。特に、やり終えた後のポイントを振り返って伝えてあげると、次への意欲につなげやすいです。
やる気をなくさないよう、できていない部分を責めるよりも、できた部分に焦点を当てて声かけをすることが大切です。
根気強く続ける
トレーニングや学習効果は、短期間ですぐに目に見える形で現れるとは限りません。ADHD傾向がある子どもは日によって集中度合いが大きく変わることもあり、思うように成果が出ない時期があるかもしれません。
しかし、脳の発達には時間がかかり、継続的な取り組みが結果を生むということを理解しておきましょう。うまくいかない日があっても、焦らずに方法を微調整しながら続けることで、徐々に前頭葉が鍛えられ、子ども自身も「やればできる」という手応えを感じられるようになっていきます。
まとめ

ADHDのお子さんの前頭葉を鍛えることは、集中力や行動の安定に繋がる重要な取り組みです。認知トレーニングや運動、日常生活でのルーティン化など、さまざまな方法があり、家庭でも無理なく始められます。
また、子どもの年齢や発達段階に合わせた適切なアプローチを選ぶことが効果を高めるポイントです。大切なのは、焦らず根気よく続けることです。小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感が育まれ、より良い成長へと繋がります。家族で協力しながら楽しく取り組んでいきましょう。




