
子どもの行動や特性が周りの子と違うことで、「もしかして発達障害?」という不安を抱えている親御さんは多いのではないでしょうか。
特に「発達障害は病気なの?」「将来はどうなるの?」という疑問や心配が頭をよぎると、どう向き合えば良いのか、正しい情報を探すのも大変です。
この記事では、まず発達障害が「病気」ではなく「生まれ持った脳の特性」であることの医学的根拠を詳しく解説します。
さらに、発達障害の種類と特徴、よく間違えられやすい疾患との違い、そして「病気じゃない」という言葉に潜む注意点についても分かりやすく紹介していきます。
最後には、明日からでも実践できる具体的な関わり方のコツもお伝えします。
この記事を読んで、子どもの特性への理解を深め、「困った子」ではなく「その子らしさ」として受け入れるヒントを見つけてください。そして、親子で前向きに歩んでいくための安心感を手に入れましょう。
発達障害は「病気」ではなく生まれ持った脳の特性

発達障害は脳の働きの違いによるもので、決して後天的に「かかる」病気ではありません。
発達障害者支援法では「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されており、生まれつきの脳の特性であることが明確に示されています。
風邪をひいたり骨を折ったりする一般的な病気とは根本的に性質が異なり、治療によって「治す」対象ではなく、理解とサポートによって「活かす」特性なのです。
発達障害の人は、他人との関係づくりやコミュニケーションに困難を感じることが多い一方で、特定の分野で優れた能力を発揮する場合も少なくありません。
この特性の凸凹が、周囲から見てアンバランスに映り、理解されにくい面があります。
重要なのは、子どもの脳が「故障している」わけではなく、多数派とは異なる個性的な働き方をしているということです。
また、発達障害は本人の努力不足や親御さんのしつけが原因ではありません。これまでの子育てが間違っていたわけでは決してないのです。
発達障害が病気ではない3つの理由

生まれつきのものであり、「治す」対象ではないから
発達障害が病気ではない最も重要な理由は、これが生まれつきの脳の特性だからです。
発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
つまり、幼いころから現れる特性で、後から「かかる」ものではないのです。
病気なら「治療して治す」ことが目標になりますが、発達障害は「理解して支援する」ことが大切です。子どもの特性を理解し、その子らしく成長できる環境を整えてあげることが何より重要なんです。
「病気」「障害」「特性」のちがい
病気とは、健康な状態から何らかの原因で体や心の調子が悪くなった状態のことです。風邪やケガのように、治療によって元の健康な状態に戻ることが期待できます。
障害とは、生まれつきや事故などによって、社会生活を送る上で何らかの困難がある状態を指します。発達障害もこの「障害」の一つですが、最近は「特性」という言葉も使われるようになりました。
特性とは、その人が持つ個性や性質のことです。発達障害に対する私たち一人ひとりの理解が必要で、一人ひとりの特性に応じた理解や支援により、その「違い」は「障害」ではなく「個性」へと変化していきます。
つまり、周囲の理解と適切な支援があれば、「困りごと」から「その子らしさ」に変わっていくということなんです。
医学的な分類でも「精神疾患」とは区別されている
医学の世界でも、発達障害は精神疾患とは明確に区別されています。
世界中で使われているアメリカ精神医学会の診断基準「DSM-5」では、発達障害は「神経発達症群(または神経発達障害群)」という大きなカテゴリーの中に位置づけられています。
「神経発達症」という名称からも分かるように、これは脳の発達の個性であって、治療が必要な病気とは考えられていません。
専門医も「治療する」のではなく「特性を理解してサポートする」という視点で子どもと向き合っています。だからこそ、家族も同じ視点を持つことが大切です。
発達障害の種類と特徴
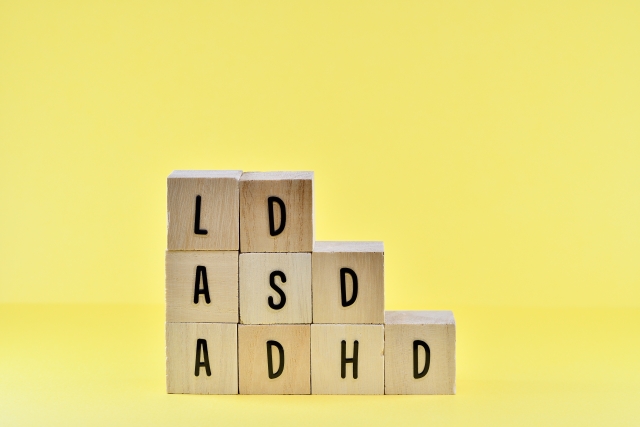
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉スペクトラム症とは、社会的コミュニケーションにおいて持続的な困難さが見られたり、日常で決まった行動や関心、動作のパターンを持ったりする障害のことです。
具体的には、以下のような特徴が見られます。
- コミュニケーションの特性:言葉や視線、表情を使った相手とのやりとりが苦手
- 対人関係の特性:友達との関係づくりが難しい
- こだわりの特性:特定のものや行動に強い関心を示す
- 感覚の特性:音や光、触覚に敏感(または鈍感)
これまで、自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などのいろいろな名称で呼ばれていましたが、2013年のアメリカ精神医学会の診断基準DSM-5の発表以降、自閉スペクトラム症(ASD)としてまとめて表現するようになりました。
大切なのは、これらの特性があっても、適切な理解とサポートがあれば、子どもは自分らしく成長していけるということです。
ADHD(注意欠陥多動性障害)
ADHD(注意欠如・多動症)は、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性がみられ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。
ADHDの特性は主に3つのタイプに分かれます。
- 不注意タイプ:集中が続かない、忘れ物が多い、整理整頓が苦手
- 多動・衝動タイプ:じっとしていられない、思ったことをすぐ口にする
- 混合タイプ:不注意と多動・衝動の両方の特性がある
特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と区別することが難しいため、幼児期にADHDの診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。
「うちの子、もしかして…」と思っても、あせる必要はありません。年齢とともに特性の現れ方も変化していくので、長期的な視点で見守ることが大切です。
LD(学習障害)
学習障害(LD)は、知的な遅れがないにも関わらず、読み書きや計算など特定の学習領域で著しい困難を示す障害です。
具体的には以下のような特徴があります。
- 読字障害:文字を読むことが困難
- 書字障害:文字を書くことが困難
- 算数障害:数の概念や計算が困難
子どもが「勉強ができない」「やる気がない」と思われがちですが、実は一生懸命取り組んでいるのに、脳の特性によって特定の分野だけが難しいのです。
この特性を理解して、子どもに合った学習方法を見つけてあげることで、必ず成長していけます。
発達障害と間違えやすい疾患・障害との違い

ASDと統合失調症をどう見分ける?
「うちの子の行動が心配で…もしかして統合失調症?」と不安になる親御さんも少なくありません。
ASDと統合失調症は、一部の症状が似ていることもありますが、根本的に異なる状態です。
ASDの特徴
- 生まれつきの特性で、幼児期から症状が見られる
- コミュニケーションや社会性の困難が持続的に続く
- こだわりや感覚の特性が一貫している
統合失調症の特徴
- 多くは思春期以降に発症する精神疾患
- 幻覚や妄想などの症状が現れる
- 症状に波があり、治療によって改善が期待できる
もし子どもの様子で気になることがあれば、一人で悩まず専門医に相談しましょう。正しい診断を受けることで、適切なサポートにつながります。
ADHDと双極症・うつ病との重なり
ADHDの子どもは、気分の浮き沈みが激しいことがあるため、双極症(躁うつ病)やうつ病と間違われることがあります。
ADHDの気分の変化
- 環境や状況によって気分が変わりやすい
- 注意が向くものによって集中度が大きく変わる
- 衝動性によって感情の表現が激しくなることがある
双極症・うつ病の気分の変化
- 理由なく気分の波が続く
- 一定期間、憂うつな気分や異常に高揚した気分が続く
- 日常生活全般に支障をきたす
ただし、発達障害があることで周囲から理解されず、叱られ続けたりすることで、うつ病などの精神疾患を二次的に発症することもあります。
このような場合は「二次障害」と呼ばれ、適切な治療とサポートで改善が期待できます。
学習障害と知的能力障害/言語障害
学習障害は、しばしば知的能力障害や言語障害と混同されることがあります。
学習障害の特徴
- 全体的な知的能力は平均的またはそれ以上
- 特定の学習領域(読み書き、計算など)のみに困難
- 得意分野と苦手分野の差が大きい
知的能力障害の特徴
- 全般的な知的機能に制限がある
- 日常生活全般で支援が必要
- 学習面だけでなく、生活スキル全体に影響
言語障害の特徴
- 言葉の理解や表現に全般的な困難
- 発音や語彙、文法に問題がある
発達障害は苦手と得意の差が大きく、知的障害は全般的に苦手なものが多い、という特徴があります。発達障害と知的障害の両方があることもあります。
正確な理解のためには、専門的な検査や評価が必要です。気になることがあれば、遠慮なく専門機関に相談してくださいね。
「病気じゃない」という言葉の落とし穴と注意点

「困りごとがない」わけではない
「発達障害は病気じゃない」と聞くと、「じゃあ問題ないってこと?」と思ってしまうかもしれません。しかし、そうではありません。
特性ゆえの困難さは、環境を調整し、特性に合った学びの機会を用意することで、軽減されると言われています。子どもが日常生活で感じている困りごとは確実に存在します。
例えば:
- 友達とうまく遊べない
- 学校の授業についていけない
- 家族とのコミュニケーションがうまくいかない
- 感覚の刺激で疲れやすい
これらの困りごとを「個性だから大丈夫」と放置してしまうのは危険です。適切なサポートと理解が必要なのは変わりません。
「個性」の一言で片づけない
「発達障害は個性」という言葉をよく耳にしますが、この言葉に頼りすぎるのも注意が必要です。
確かに発達障害は、その人らしさの一部です。でも、「個性だから」と言って具体的な支援をしなければ、子どもの困りごとは解決されません。
大切なのは:
- 個性として受け入れること
- 同時に、必要な支援を提供すること
- 子どもが自信を持って生活できる環境を作ること
この両方のバランスを取ることが、子どもの成長にとって最も大切です。
「二次障害」という病気のリスク
発達障害そのものは病気ではありませんが、適切な理解やサポートがないと「二次障害」と呼ばれる精神的な問題が生じることがあります。
発達障害の特性が理解されないまま、叱られたり否定的な対応をされたりすることで、自尊心が低下し、うつ病や不安障害、不登校などの二次障害を引き起こすことがあります。
二次障害の例
- うつ病、不安障害
- 不登校、引きこもり
- 自傷行為、暴力行為
- 摂食障害
発達障害があるからといって必ずしも二次障害が起きるわけではありません。周囲の適切な理解や支援により、発達障害から起きる生きづらさを軽減し、二次障害を回避することもできます。
つまり、発達障害は病気ではないけれど、周囲の理解不足によって本当の「病気」につながる可能性があるということです。だからこそ、早期の理解と適切なサポートが何より大切です。
明日から親ができる発達障害の子どもとの5つの関わり方

「できないこと探し」より「できたこと」探し
日々の生活の中で、つい「また忘れ物をして…」「どうして片付けられないの…」と、子どものできないことに目が向いてしまうことがあります。
しかし、発達障害の子どもには「できたこと」を見つけてほめることが何より大切です。
今日からできる具体的な方法
- 小さなことでも「できたね!」と声をかける
- 「○○ができるようになったね」と成長を認める
- 努力した過程を褒める(結果だけでなく)
- 家族みんなで子どもの良いところを見つけて共有する
例えば、宿題を最後まで終わらせられなくても「30分間集中して取り組めたね」「字が丁寧に書けているね」など、過程や部分的な成功を認めてあげましょう。
子どもの自己肯定感が高まることで、新しいことにもチャレンジしやすくなります。
「どうしてできないの?」から「どうしたらできるかな?」へ
発達障害の子どもは、「どうしてできないの?」と問いかけられても、明確に答えることが困難な場合が多くあります。これは、脳の特性に起因するものであり、本人自身も理由を言語化しにくいためです。
質問の仕方を変えてみましょう
- ×「どうして宿題ができないの?」
- 〇「宿題をするには何があると良いかな?」
- ×「なんで片付けられないの?」
- 〇「片付けやすくするには、どうしたら良いと思う?」
このように、問題解決に向けた前向きな質問に変えることで、子どもも一緒に考えることができます。そして、子ども自身が解決策を見つける力も育っていきます。
「伝わる」工夫をしてみる
発達障害の子どもには、情報を視覚的に伝えることがとても効果的です。
具体的な工夫例
- 一日のスケジュールを絵カードで作る
- 片付ける場所に写真やイラストを貼る
- やることリストを手順ごとに分けて書く
- タイマーを使って時間を視覚化する
言葉よりも、目で見て分かる情報の方が理解しやすい場合があります。理解できる言葉と、「絵カード」のような視覚情報を添えて説明すると理解しやすくなります。
また、一度にたくさんの指示を出すのではなく、一つずつ確実に伝えることも大切です。
家庭を「安心できる基地」にする
外の世界で頑張っている子どもにとって、家庭は何よりも安心できる場所であるべきです。
安心できる家庭環境のポイント
- 子どもの特性を家族全員が理解する
- 失敗しても大丈夫だと伝える
- 子どものペースを尊重する
- 感覚過敏がある場合は、環境を調整する
子どもの癇癪がひどい時でも、叱らずに少しの時間待つことで早く混乱から抜け出すこともあります。家庭が安心できる基地になることで、子どもは外の世界でも自信を持って挑戦できるようになります。
「チーム」で育てる意識を持つ
発達障害の子どもの子育ては、一人で抱え込まず「チーム」で行うことが大切です。
チームのメンバー例
- 家族(パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん)
- 学校の先生
- 発達支援の専門家
- 医療機関の先生
- 同じような経験をする親御さんたち
それぞれの立場から、子どもをサポートしてもらいましょう。情報を共有し、一貫した対応をすることで、子どもはより安定した環境で成長できます。
一人で悩まず、遠慮なく周りの人に相談することをおすすめします。きっと、温かく支えてくれる人たちがいるはずです。
まとめ

発達障害は「病気」ではなく、生まれ持った脳の特性です。子どもの子育てが間違っていたわけでも、子どもに問題があるわけでもありません。
大切なのは、子どもの特性を理解し、その子らしく成長できる環境を整えてあげることです。「できないこと」ではなく「できること」に注目し、子どもの自己肯定感を育てていきましょう。
発達障害の子どもは、適切な理解とサポートがあれば、必ず自分らしく輝ける未来が待っています。二次障害を防ぐためにも、早期の理解と継続的な支援が重要です。
一人で抱え込まず、家族、学校、専門機関と「チーム」になって、子どもの成長を見守っていきましょう。子どもの将来は、きっと明るいものになるはずです。
子どもの特性を「困ったもの」ではなく「その子らしさ」として受け入れ、一緒に歩んでいけば、親子共に成長していける素晴らしい道のりになるでしょう。




