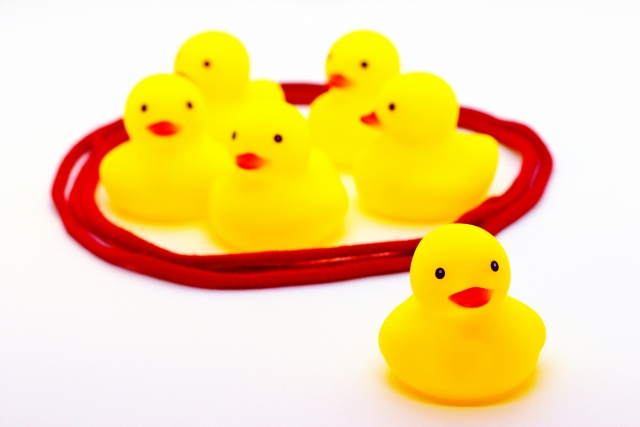
「うちの子、もしかして発達障害?」そう思って病院を受診したものの、診断がつかずに戸惑ってしまう親御さんは少なくありません。
診断がないことで公的な支援を受けにくく、周囲からは「しつけの問題」と誤解されてしまうこともあり、一人で悩みを抱え込んでしまいがちです。
でも実は、発達障害のような特性を見せる子どもの中には、HSC(人一倍敏感な子)や愛着の問題、生まれ持った気質など、別の要因が関わっているケースが意外に多いのです。
この記事では、発達障害と間違われやすい5つのケースを詳しく解説し、特に似ていると言われるHSCと発達障害の違いについて分かりやすくお伝えします。
さらに、子どもの心を楽にする具体的な関わり方のコツや、診断がなくても相談できる身近な窓口についても紹介していきます。
この記事を読んで、子どもの特性への理解を深め、その子らしい成長を支えるためのヒントを見つけてください。
発達障害と間違われやすい、子どもの5つのケース

HSC(人一倍敏感な子)
HSCとは「Highly Sensitive Child(人一倍敏感な子)」の略で、生まれつき感受性が非常に高く、敏感な気質を持つ子どものことです。日本の子どもの約5人に1人がHSCの気質を持っているとされています。
HSCの子どもは、周りの環境の変化や刺激に人一倍敏感に反応します。
音、光、におい、肌触りなどの感覚刺激に敏感で、他の子が平気な音でも不快に感じたり、服の素材にこだわったりすることがあります。また、人の気持ちや場の空気を敏感に察知するため、友達が悲しんでいると自分も一緒に泣いてしまったり、大人の表情の変化にいち早く気づいたりします。
集団の中では疲れやすく、一人の時間を必要とすることも多いでしょう。新しい環境や予定の変更に対して、他の子より強い不安を感じることもあります。
でも、これらの特徴は病気ではなく、生まれ持った気質であり、医学的に診断される疾患ではありません。
愛着形成の問題
愛着とは、子どもが特定の養育者との間に築く心の絆のことを指します。この愛着が適切に形成されなかった場合、発達障害に似た行動や症状が現れることがあります。
例えば、養育者との分離不安が強すぎたり、逆に無関心すぎたりする行動は、自閉症スペクトラム障害の症状と混同される場合があります。
また、落ち着きがなく集中できない様子は、ADHDと間違われることもあるでしょう。
愛着の問題は、適切な関わり方と環境の整備により改善される可能性が高いため、早期の気づきと対応が重要になります。
専門的な支援を受けながら、親子の関係性を丁寧に築き直していくことで、子どもの行動や情緒が安定してくることが期待できます。
生まれ持った「気質」
気質とは、生まれつき持っている行動や反応のパターンのことで、発達障害とは区別される概念です。活動性が高い子ども、慎重で新しいことを嫌がる子ども、感情の起伏が激しい子どもなど、さまざまなタイプがあります。
これらの気質的な特徴は、環境や状況によって問題行動のように見えることがありますが、適切な理解と対応により活かすことができる個性です。
例えば、活動性が高い子どもは「落ち着きがない」と捉えられがちですが、エネルギッシュで行動力があるという長所として見ることもできます。
慎重な気質の子どもは「引っ込み思案」と思われることもありますが、じっくり考えて行動する慎重さという強みを持っています。
気質を理解し、その子に合った環境や関わり方を工夫することで、子どもは自分らしく成長していくことができるでしょう。
一時的な環境の変化によるストレス
転居、転園、家族構成の変化、親の離婚など、環境の大きな変化は子どもにとって大きなストレスとなります。このようなストレスが原因で、一時的に発達障害のような症状が現れることがあります。
例えば、新しい保育園や幼稚園に入った直後、弟や妹が生まれた後、引っ越しをした後などに、普段は見られない行動が現れることがあります。
また、言葉の発達が一時的に遅れたり、以前できていたことができなくなったりする「退行」という現象が起こることもあります。
これらの症状は環境に慣れ、ストレスが軽減されることで自然に改善されることが多いのが特徴です。ただし、症状が長期間続く場合や悪化する場合は、専門機関への相談を検討することが大切になります。
知的発達のゆっくりさ
知的発達がゆっくりな子どもの場合、発達障害と間違われることがあります。
知的発達の遅れは、言語理解や学習面での困難として現れることが多く、これらが自閉症スペクトラム障害や学習障害と混同される場合があるのです。
しかし、知的発達がゆっくりでも、その子なりのペースで着実に成長していく場合は、発達障害とは区別して考える必要があります。大切なのは、その子の発達のペースを理解し、適切な支援と環境を提供することです。
無理に他の子どもと同じレベルを求めるのではなく、その子が持っている可能性を最大限に引き出すような関わり方が重要になります。専門機関での継続的な観察により、発達の状況を正しく把握し、必要に応じて支援を受けることで、その子らしい成長を促すことができるでしょう。
最も似ている「HSC」と発達障害、何が違う?

HSCとは?
HSC(Highly Sensitive Child)は、アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念で、生まれつき感覚処理感受性が高い子どものことを指します。
HSCには、物事を深く考え抜く(Depth of processing)、刺激を過剰に受けやすい(Overstimulation)、感情の反応が強く共感力が高い(Emotional reactivity / Empathy)、些細な刺激を察知する(Sensitivity to subtleties)という4つの特徴があります。
他人の気持ちを敏感に察知するため、周囲の人が不機嫌だと自分も不安になったり、映画やテレビの暴力的なシーンに強く反応したりします。
集団活動では刺激が多すぎて疲れやすく、一人の時間を必要とすることも特徴の一つです。
これらの特性は病気や障害ではなく、その子が持って生まれた個性として理解することが大切になります。
発達障害との違い
HSCと発達障害の最も大きな違いは、HSCが「気質」であり、発達障害が「脳の機能的な特性」であるという点です。
HSCの子どもは感覚に敏感であっても、適切な環境が整えばコミュニケーション能力や学習能力に問題はありません。一方、発達障害の場合は、環境を整えても根本的な特性は変わらず、継続的な支援や配慮が必要になることが多いです。
また、HSCの子どもは共感能力が非常に高く、他人の感情を深く理解できるという長所を持っています。発達障害の中でも自閉症スペクトラム障害の場合、他人の気持ちを理解することに困難を感じることが多いため、この点で大きく異なります。
ただし、HSCと発達障害を併せ持つ子どももいるため、専門機関での適切な評価を受けることが重要です。
子どもの心を楽にする関わり方のヒント

環境を調整する
子どもが過ごしやすい環境を整えることは、どのような特性を持つ子どもにとっても重要です。
感覚に敏感な子どもの場合、音や光の刺激を調整したり、触感の良い衣類を選んだりすることで、日常生活のストレスを大幅に軽減できます。
例えば、蛍光灯の光が苦手な子どもには間接照明を使ったり、騒音が気になる場合はカーペットを敷いて音を吸収したりする工夫が効果的です。まずは、子どもがどんな刺激を苦手としているのかを観察することから始めてみてください。
まずは、子どもがどんな刺激を苦手としているのかを観察することから始めてみてください。また、子どもが安心できる「避難場所」を家の中に作ることも大切になります。
疲れたときや不安になったときに、一人でゆっくりできるスペースがあることで、子どもの心理的な安定につながります。学校や園でも、担任の先生と相談して、子どもが過ごしやすい環境づくりに協力してもらうことをおすすめします。
気持ちを言葉にする手伝いをする
子どもが自分の気持ちを上手に表現できないとき、大人が気持ちを言葉にする手伝いをすることが重要です。
「いま、悲しい気持ちなんだね」「びっくりして怖かったんだね」というように、子どもの感情を代弁してあげましょう。これにより、子どもは自分の感情を客観視できるようになり、感情のコントロールが上手になっていきます。
また、気持ちを表現する言葉のバリエーションを増やしてあげることも大切です。「いやだ」という表現しかできない子どもに、「困っている」「心配」「不安」など、より具体的な感情を表す言葉を教えてあげましょう。
感情の言語化ができるようになると、子ども自身が問題解決能力を身につけていくことにもつながります。
成功体験を積ませる
「自分はできるんだ!」という小さな成功体験の積み重ねは、子どもの自信、つまり自己肯定感を育む上で何よりも大切な栄養になります。
発達に凸凹があったり、敏感さゆえに挑戦が苦手だったりする子どもは、失敗体験から自信を失いがちです。だからこそ、大人が少しだけハードルを下げてあげて、「ちょっと頑張ればできる」という課題を用意してあげることが重要です。
例えば、着替えが苦手なら、まずはズボンを履くところだけ自分でやってみる、など、課題を細かく分解するのも一つの手です。そして、できたら「すごい!最後までできたね!」と、結果だけでなく頑張った過程を具体的に褒めてあげてください。
絵が得意な子ども、音楽が好きな子ども、体を動かすことが好きな子どもなど、それぞれの強みを活かせる場面を意識的に作ってあげましょう。
子どもの「好き」や「得意」なことを見つけて、それを存分に発揮できる場を作ってあげることも、自信を育む素晴らしい機会になります。
親自身の心を守る
子どもへの適切な関わりを続けるためには、親自身の心の健康を維持することが欠かせません。
周囲からの理解が得られず孤立感を感じたり、子どもの将来への不安で心が重くなったりすることは、多くの親が経験することです。
まずは、自分の気持ちを否定せず、「不安になっても当然」「完璧な親である必要はない」と自分自身を受け入れることから始めましょう。
信頼できる人に相談したり、同じような悩みを持つ親同士でつながったりすることで、孤独感を軽減できます。また、自分だけの時間を意識的に作り、好きなことをしてリフレッシュすることも大切です。
親の心が安定していることで、子どもも安心して過ごすことができるようになります。
どこに相談すればいい?一人で悩まないための相談先

市区町村の保健センター、子育て支援センター
最も身近で相談しやすいのが、お住まいの市区町村にある保健センターや子育て支援センターです。
これらの施設では、保健師や子育て支援員が子どもの発達や育児に関する相談を無料で受け付けています。発達に関する心配事があるときは、まずここで相談してみることをおすすめします。
必要に応じて、より専門的な機関への紹介もしてもらえるため、最初の窓口として活用できます。
また、同年代の子どもを持つ親同士が交流できる場も提供されており、情報交換や悩みの共有ができる貴重な機会になります。定期的に開催される育児教室や講座に参加することで、子どもとの関わり方のヒントも得られるでしょう。
学校の先生、スクールカウンセラー
子どもがすでに園や学校に通っている場合、担任の先生やスクールカウンセラーは、最も身近な支援者となります。まずは、家庭での子どもの様子や、保護者として心配に思っていることを具体的に担任の先生に伝えてみましょう。
その上で、園や学校での集団生活の様子を教えてもらい、情報を共有することが、的確なサポートへの第一歩となります。
例えば、「静かな場所でクールダウンする時間を設けてもらう」「指示は一つずつ、短く伝えてもらう」といった具体的な配慮をお願いすることも可能です。
また、週に数回学校に来ているスクールカウンセラーは、臨床心理士などの資格を持つ心の専門家です。子ども本人との面談はもちろん、保護者だけの相談にも応じてくれるので、専門的な視点からのアドバイスがもらえます。
かかりつけの小児科
赤ちゃんの頃から子どもの成長を見守ってくれている、かかりつけの小児科医も、発達に関する悩みを打ち明けられる心強い存在です。日頃の診察で子どもの様子をよく知っているため、発達の遅れや特性について、客観的な視点でアドバイスをくれることがあります。
一見、発達の問題に見える行動の背景に、実はアレルギーや貧血といった身体的な問題が隠れている可能性も否定できません。そうした医学的な観点から、まずは全身状態をチェックしてもらえるというメリットもあります。
もし、より専門的な診査や診断が必要だと判断された場合には、発達外来のある病院や地域の療育センターなど、適切な専門機関を紹介してもらうこともできます。
大きな専門病院へ直接行くのは敷居が高いと感じる方にとって、信頼できる「つなぎ役」となってくれるでしょう。
発達障害者支援センター、児童相談所
より専門的なアドバイスや継続的な支援を求める場合には、各都道府県や指定都市に設置されている「発達障害者支援センター」が頼りになります。
このセンターは、発達障害のある人やその家族からのあらゆる相談に応じ、適切な支援につなぐための専門機関です。
診断の有無にかかわらず、発達が気になる段階から相談することができ、必要に応じて発達検査を受けたり、個別の支援計画を作成してもらったりすることも可能です。
また、「児童相談所」と聞くと、虐待対応のイメージが強いかもしれませんが、本来は18歳未満の子どものあらゆる問題に対応する相談機関です。
発達の遅れや障害に関する相談にも応じており、心理判定員による専門的な見立てや、療育手帳の判定などを行っています。
どちらも敷居が高いと感じるかもしれませんが、子どもの健やかな成長を願う強力な味方になってくれます。
まとめ

子どもの行動が気になって「発達障害かもしれない」と心配になったとき、実際には別の要因が関わっている場合があることをお伝えしました。
HSC、愛着の問題、生まれ持った気質、環境の変化によるストレス、知的発達のゆっくりさなど、発達障害と似た特性を示すケースは意外に多いものです。
大切なのは、子どもの特性を正しく理解し、その子に合った関わり方や環境づくりを心がけることです。
環境の調整、気持ちの言語化の手伝い、成功体験の積み重ね、そして親自身の心のケアなど、今日からできることはたくさんあります。
一人で抱え込まず、保健センター、学校、かかりつけ医、専門機関など、さまざまな相談先を活用しながら、子どもの成長を支えていってください。
どのような特性を持つ子どもでも、適切な理解と支援があれば、必ずその子らしい成長を遂げることができます。子どもの笑顔と成長を信じて、一歩ずつ前進していきましょう。




